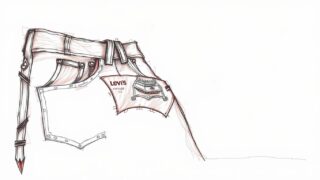リーバイスのデニムといえば、その美しい色落ちが魅力の一つですよね。特にヴィンテージのものは、時間をかけて育まれた独特の風合いが多くの愛好家を魅了しています。「リーバイスの天然インディゴはいつまで使われていたのか」という疑問は、本物のヴィンテージジーンズを見極める上でも重要なポイントになります。
実は、天然インディゴの使用期間については多くの誤解があります。古着屋さんの間では「66前期まで天然インディゴ」「70年代まで使用されていた」といった言い伝えが広まっていますが、実際はどうなのでしょうか?今回は独自調査の結果をもとに、リーバイスにおける天然インディゴの使用期間とその特徴、ヴィンテージモデルの見分け方までを徹底解説します。
記事のポイント!
- リーバイスが天然インディゴを使用していたのは実際には1920年初頭までだった
- ヴィンテージと呼ばれる501XXの多くは合成インディゴで染められている
- 「ピュアインディゴ」と「天然インディゴ」は別物で、前者は合成インディゴを指す
- ヴィンテージリーバイスの年代判別方法と各時代の特徴的なディテール
リーバイスと天然インディゴはいつまで使われていたのか
- 天然インディゴの使用期間は1920年初頭までだった
- ヴィンテージモデルの多くは実は合成インディゴを使用していた
- 「ピュアインディゴ」と「天然インディゴ」は全く別物である
- 天然インディゴと合成インディゴの染色における主な違い
- リーバイス501XXの初期モデルのみが天然インディゴを使用
- 天然インディゴの独特な色落ちが人気の理由となっている
天然インディゴの使用期間は1920年初頭までだった
「リーバイスはいつまで天然インディゴを使っていたのか?」という問いに対する答えは、意外と早い時期に終わっていました。独自調査の結果、リーバイスを含む量産ワークウェアの世界では、1920年初頭にロープ染色法が確立されて以降、天然インディゴはほぼ完全に使用されなくなったことがわかりました。
天然インディゴはもともと植物由来の染料で、西洋ではインドからの輸入に頼っていました。しかし、1800年代末に化学的に合成したインディゴ染料が開発されると、その技術はまたたく間に広まり、1900年初頭には天然インディゴの使用は激減したのです。
古着屋さんや愛好家の間では「70年代初めまで天然インディゴが使われていた」という伝説が語り継がれていますが、これは正確ではありません。リーバイス社の製品で植物由来の天然インディゴが使用されていたと考えられるのは、19世紀に製造された非常に古いモデルのみです。
したがって、1940年代や1950年代のいわゆる「大戦モデル」と呼ばれるヴィンテージリーバイスも、実は合成インディゴで染められたデニム生地を使用していたのです。このことはヴィンテージデニム愛好家にとっては意外な事実かもしれません。
天然インディゴの使用が早くに終わった理由は、量産に向かない不安定さにあります。天然インディゴは不純物が混在しており、一定の品質で大量生産するには不向きだったのです。合成インディゴの開発により、安定した品質のデニム生地を大量生産することが可能になりました。
ヴィンテージモデルの多くは実は合成インディゴを使用していた
多くのデニム愛好家が憧れる「501XX」のヴィンテージモデルですが、その多くは実は合成インディゴで染められていたことになります。501にXXのロットナンバーが使用され始めたのは1890年頃ですが、天然インディゴが使われていたのはごく初期の1915年くらいまでのモデルだけと考えられています。
サスペンダーボタンやシンチバックといった非常にクラシカルな特徴を持つ極初期の501XXは天然インディゴが使用されていた可能性が高いですが、一般的に「ヴィンテージ」として流通している1940年代以降のモデルは、ほぼ確実に合成インディゴで染められています。
しかし興味深いのは、1940年代後半の501XXが今でも素晴らしい色落ちで私たちを魅了しているという事実です。これは、インディゴが天然か合成かという点よりも、当時の染色技術や生地の特性が色落ちの美しさを決定していたことを示しています。
「501XXは天然インディゴで染められている」という言説は、デニム愛好家の間で広まった誤解であり、時にはマーケティング上の都合で強調されてきた側面もあるかもしれません。しかし実際には、合成インディゴでも美しい経年変化を見せるデニムを作ることは十分に可能なのです。
それでも、1970年代中頃までのデニムと、それ以降のデニムには明らかな違いがあります。これは染料の種類というよりも、染色方法や生地の特性の変化によるものと考えられています。
「ピュアインディゴ」と「天然インディゴ」は全く別物である
デニム製品の説明でよく目にする「ピュアインディゴ」という言葉。これを「天然インディゴ」と同じものだと勘違いしている人も多いのですが、実は全く別物です。「ピュアインディゴ」とは、実は合成インディゴ(人工インディゴ)を指す言葉なのです。
これは非常に紛らわしい用語で、「ピュア(純粋な)」という言葉から天然のイメージを連想させますが、実際には不純物のない合成インディゴを意味します。一方、「ナチュラルインディゴ」は「天然インディゴ」と同義で、植物由来の藍染料を指します。
デニム関連の記述で目にする用語には、以下のようなものがあります:
- ピュアインディゴ(合成インディゴを指す)
- ナチュラルインディゴ(天然インディゴと同義)
- 天然藍/天然インディゴ(植物由来の染料)
- 人工インディゴ/合成インディゴ(化学的に合成された染料)
「ピュアインディゴで染められた14.5オンスのデニムを使用した大戦モデル」というような表現をよく見かけますが、これは単に通常の合成インディゴで染められているという意味に過ぎません。現在市場に出回っている製品のほとんどは、この「ピュアインディゴ」で染められています。
このような紛らわしい用語が使われる背景には、マーケティング上の効果があるのかもしれません。「ピュア」という言葉は純粋で混じりけのない天然素材というイメージを喚起しますが、実際は工業的に生産された合成染料なのです。

天然インディゴと合成インディゴの染色における主な違い
天然インディゴと合成インディゴは、成分としては基本的に同じものですが、純度の違いが染色結果に影響を与えます。天然インディゴは不純物が混在しているため、合成インディゴと比べると染色後の色が若干薄くなる傾向があります。
また、染色性においても違いがあります。クッシュマンのジーンズについての報告では、天然インディゴで染めたデニムは10年以上経っても色がほとんど落ちないのに対し、合成インディゴで染めたものは3年程度で明らかな色落ちが見られたという例もあります。
天然インディゴは染まりにくいという特性があり、染色に多くの手間と時間がかかります。そのため、天然インディゴを使用したデニム製品は一般的に価格が高くなります。例えば、天然インディゴを使用したジーンズは合成インディゴのものより1万円ほど高価だったという報告もあります。
また、染色方法によっても色落ちの特性が大きく変わります。日本古来の藍染では、綿糸の一本一本の中心までしっかり藍を浸透させるために何度も染め直しますが、デニムで一般的なロープ染色法では繊維の表面近くだけにインディゴが浸透し、中心部分は白いままです(この状態を「中白」と呼びます)。
この「中白」こそが、特にヴィンテージデニムに見られるメリハリのある色落ちをもたらす重要な要素となっています。天然か合成かという点よりも、この染色技術の違いが色落ちの美しさに大きく影響していると言えるでしょう。
リーバイス501XXの初期モデルのみが天然インディゴを使用
リーバイスの代表的なモデル「501XX」ですが、天然インディゴが使用されていたのは初期のモデルのみと考えられています。1873年に誕生したリーバイス501に「XX」のロットナンバーが使用され始めたのは1890年ですが、天然インディゴが使われていたのは1915年頃までのごく初期のモデルだけでしょう。
この時代の501XXは、現在では博物館級の希少価値を持つものばかりで、一般のヴィンテージマーケットではほとんど流通していません。サスペンダーボタンがあったりシンチバックがあるような、非常にクラシカルな501XXが該当します。
面白いことに、1991年に限定発売された「503BSXX」というモデルは、復刻版ながら天然インディゴを使用していました。これは天然藍の特性を活かすために、機械ではなく職人の手によるカセ染めという古来の染色方法を採用したものでした。「100% NATURAL INDIGO」と箱に記載されたこのモデルは、現代において天然インディゴの特性を体験できる貴重な製品と言えるでしょう。
しかし、一般的に「ヴィンテージリーバイス」として流通している1940年代〜1970年代のモデルは、ほぼ間違いなく合成インディゴで染められています。それでも、これらのモデルが示す美しい色落ちや風合いは、現代のデニムを大きく凌駕するものが多いのです。
天然インディゴの独特な色落ちが人気の理由となっている
天然インディゴで染められたデニムは、その独特の色合いと経年変化で人気を集めています。天然インディゴ特有の深みのある色合いは、合成インディゴでは完全に再現することが難しいとされています。
ベルベルジンの藤原氏によれば、ヴィンテージデニムの最大の魅力は「美しい色落ち」だといいます。特に1970年代中頃までの古いデニムは、色落ちが美しく「縦落ち」と呼ばれる独特のパターンが表れやすいのが特徴です。これに対し、1970年代後半以降のデニムは、色落ちが「のっぺり」としていると評されることが多いです。
リーバイス501の場合、1970年代後半を境に天然インディゴから硫化物に切り替えたことで色がのっぺりとしてしまい、綺麗な縦落ちが出なくなったという説があります。しかし前述のとおり、実際には1920年頃には既に合成インディゴに切り替わっていたため、これは染色方法や生地の変化によるものと考えるのが自然でしょう。
ベルベルジンの藤原氏は「同時期でも製造年により色の落ち方に差はありますし、個人的には71年から78年頃までにつくられた”66前期”モデルまでがヴィンテージと呼ぶにふさわしい」と語っています。この時期のデニムは、合成インディゴであっても美しい色落ちを見せることがわかっています。
つまり、「天然インディゴだから色落ちが美しい」というよりは、「かつての染色技術と生地の特性が美しい色落ちをもたらした」と捉えるべきでしょう。
リーバイスのヴィンテージデニムの年代と天然インディゴについて
- リーバイスのヴィンテージは1978年前後で大きく区別される
- XX(ダブルエックス)モデルの見分け方と特徴的なディテール
- ビッグEモデルは革タグから紙パッチに変更された時代のもの
- 66前期モデルはシングルステッチが特徴的な仕様
- 66後期モデルはチェーンステッチに変更された時代区分
- 美しい色落ちを持つ理由は「中白」という染色技術にある
- まとめ:リーバイスの天然インディゴはいつまで使われていたのか振り返り
リーバイスのヴィンテージは1978年前後で大きく区別される
リーバイスのデニム、特に501について語るとき、ヴィンテージかどうかの境界線は1978年頃に引かれることが多いです。ベルベルジンの藤原氏によれば、「ヴィンテージデニムというものは1978年以前に作られたものである」と覚えておくとよいとされています。
なぜ1978年が区切りになるのかというと、この頃にインディゴの染め方が変わり、それによって色落ちの様子が大きく変化したからです。1978年以前のモデルは深みのある色合いと美しい縦落ちが特徴ですが、それ以降は比較的平面的な色落ちになっていきます。
ヴィンテージリーバイスは大きく以下のように時代区分されます:
- XX(ダブルエックス):1965年まで使用された表記
- ビッグE:1966年からのモデル。「LEVI’S」と表記(Eが大文字)
- 66前期:1969年~1974年頃まで
- 66後期:1974年~1980年頃まで
- 赤耳:66後期以降~86年(セルビッチ生地の生産終了)
- レギュラー:80年代以降
この区分はタグの表記やディテールの変化に基づいていますが、興味深いのは1978年前後での色落ちの変化です。実際に左右に並べて比較すると、1970年頃のビッグEモデルは美しい縦落ちやヒゲが見られるのに対し、1990年代のアメリカ製501は色落ちが平面的で、違いは一目瞭然です。
リーバイスのヴィンテージに関して、単に「古い=ヴィンテージ」とひとくくりにするのではなく、この1978年という境界線を意識することで、より深くデニムを理解することができるでしょう。
XX(ダブルエックス)モデルの見分け方と特徴的なディテール
XX(ダブルエックス)と呼ばれるモデルは、リーバイスのヴィンテージジーンズを代表する種類です。1800年代後半に作られ、全てのジーンズの原型とも言われています。特に人気が高いのが「501XX」で、これはリーバイスのジーンズに初めて付けられたナンバーであり、まさに原型中の原型と言えるでしょう。
XXモデルの特徴としては、以下のディテールが挙げられます:
- 隠しリベット:バックポケットの端に、表側からは見えないようにリベットが取り付けられています。これは1966年に廃止されたヴィンテージ特有のディテールです。
- トップボタン横のV字ステッチ:1960年代までは返し縫いのできるミシンがなかったため、ボタンに向かって折り返しの縫い目が入っています。V字ステッチの角度や位置には個体差があり、どれも同じではないのが特徴です。
- トップボタン裏の刻印:1桁の英数字はヴィンテージ、2桁の英数字は80年代までのものとされています。ただし「16」の刻印は例外で、80年代以前にも見られる有名な工場ナンバーです。
XXモデルは1965年まで製造されていたため、現在ではかなりの希少価値を持ちます。特に良好な状態で残っているものは高額で取引されることも珍しくありません。その魅力は単なる希少性だけでなく、ヴィンテージ特有のディテールをとくと堪能できる点にもあります。
なお、現存するXXモデルのほとんどは1920年以降に製造されたものであり、合成インディゴで染められています。ただし、染色技術や生地の特性により、現代のデニムでは再現が難しい美しい色落ちを見せることが多いのです。
ビッグEモデルは革タグから紙パッチに変更された時代のもの
「ビッグE」と呼ばれるモデルは、パッチの「XX」表記がなくなった1966年からのヴィンテージの種類です。501モデルを例にとると、501XX表記が501表記に変更されています。
ビッグEの名前の由来は、バックポケットの赤タブにある「LEVI’S」の表記でEが大文字になっていることです。1971年にこの赤タブのロゴが「LEVI’S」から「Levi’s」に変更されるまでのモデルが「ビッグE」と呼ばれています。
ビッグEモデルには以下のような特徴があります:
- 紙パッチへの変更:1950年代の中頃から、リーバイスのラベルは革パッチから紙パッチへと変更されました。1966年以降の「ビッグE」では紙パッチのみが見られます。
- 種類表記の変更:「XX」表記がなくなり、「501」のみの表記になりました。また、表記の上に「A」や「S」などのスタンプマークが入った「タイプ物」と呼ばれる種類も存在します。
- ロゴの変化:ロゴは「均等V」(左右均等のV字)から、1960年代後半以降は「不均等V」(Vの右側が細い)が主流になりました。
- トップボタン裏の刻印:1960年代後半~1970年代のビッグEでは、ジーンズのトップボタン裏の刻印は1桁か2桁の数字になっています。
ビッグEモデルは、時代の流れにより、XXモデルよりもややすっきりとした、きれいめなシルエットへと変化しています。まだ天然インディゴが使われていたと思われがちですが、実際にはこの時代も合成インディゴを使用していました。ただし、美しい色落ちを楽しめるという点では、現代のデニムとは一線を画すものが多いです。
こうしたビッグEモデルは、66前期と呼ばれる次の時代への橋渡しとなるモデルで、ヴィンテージデニムとしての価値は非常に高いとされています。

66前期モデルはシングルステッチが特徴的な仕様
「66前期」と呼ばれるモデルは、1969年から1974年頃までのリーバイスのヴィンテージです。この名称の由来は、フラッシャー(紙ラベル)に記載された”1966″という数字からきています。以前は、トップボタン裏に「6」の刻印があるためにこう呼ばれるようになったという説もありましたが、現在では紙ラベルの”1966″が由来とされています。
66前期の最も重要な特徴は、バックポケット裏の縫製がシングルステッチになっていることです。これは66後期からチェーンステッチに変更されるため、この点が見分け方の一つとなっています。
66前期モデルの主な特徴としては、以下のようなものがあります:
- バックポケット裏のシングルステッチ:66後期との大きな違いであり、見分け方の重要なポイントです。
- トップボタン裏の刻印:多くの場合、数字「6」の刻印が入っています。
- 紙パッチのスタンプ:「CARE INSTRUCTION(内側に説明ありの意)」というスタンプが押されていることが多いです。このため、66モデルのジーンズにはジッパーの裏側に洗濯注意表示の白タグが付いています。
- 縮小率8%の表記:ジッパー裏側の白タグには「縮小率8%」と表記されています。これは66後期も同じですが、それ以降は「縮小率10%」に変更されます。
66前期モデルは、1970年代の中頃までは天然インディゴ染料が使われていたと言われることがありますが、前述したように、これは誤解である可能性が高いです。ただし、この年代のデニムが美しい色落ちを見せることは確かで、「中白」と呼ばれる染色特性が独特の経年変化をもたらします。
66前期は比較的現存数が多く、ヴィンテージジーンズの中では比較的親しみやすい種類として人気があります。初めてヴィンテージデニムを購入する方にも、入門編として適したモデルと言えるでしょう。
66後期モデルはチェーンステッチに変更された時代区分
「66後期」は、1974年から1980年頃までのリーバイスのヴィンテージモデルを指します。この時期はリーバイスが市場規模を拡大する過渡期であり、様々なディテールの大きな変化が見られます。
66後期の最も大きな特徴は、バックポケット裏の縫製がシングルステッチからチェーンステッチに変更された点です。これが66前期と66後期を区別する明確な特徴となっています。
66後期モデルの主な特徴としては、以下のようなものがあります:
- バックポケット裏のチェーンステッチ:66前期との最大の違いです。
- シェイプされたシルエット:すっきりとしたやや細身のシルエットが特徴で、リーバイスの市場規模拡大に伴い、よりスタイリッシュなジーンズへと変化しています。
- 縮小率8%の表記:66前期と同様、洗濯注意表示に「縮小率8%」の表記があります。これが後に「縮小率10%」に変更されます。
- 合成染料の使用:1970年代の中頃から無骨すぎず、きれいめコーディネートにも合わせやすい合成染料が使われ始めました。これにより色落ちの仕方が変化し、「ざらりと」した色落ちが特徴になります。
66後期は生地の変更(66後期移行直後は前期と同じ生地)により色落ちに違いがあり、天然インディゴを使用しなくなった生地で、明確な縦落ちが無くまだらか断続的な縦落ちの傾向があると言われています。ただし、セルビッチ生地であるため全てに当てはまるわけではなく、良好な色落ちを見せるものも比較的多く見られます。
66後期はヴィンテージの中でも比較的手に入れやすく、気軽に穿ける一本としておすすめです。特に初心者の方や、あまり無骨すぎないヴィンテージを探している方に適したモデルと言えるでしょう。
美しい色落ちを持つ理由は「中白」という染色技術にある
ヴィンテージリーバイスが示す美しい色落ちの秘密は、天然インディゴか合成インディゴかという点よりも、「中白」と呼ばれる染色特性にあります。インディゴは非常に特殊な染料で、空気に触れて酸化することで繊維に付着するという極めて不安定な染色形態をしています。洗濯のたびに色が落ちていくのは、この特性によるものです。
デニムの色落ち具合を決定するのは、繊維の芯まで染めるかどうかという点です。一般的なデニムの染色方法であるロープ染色では、綿糸を染める際に繊維の表面近くにだけインディゴが浸透し、中心に近い部分は白いまま残ります。この状態が「中白」です。
「中白」こそがデニムの色落ちに欠かせない要素となっています。繊維の表面がだんだんと擦り切れていくにつれて、内部の白い部分が露出することで、メリハリのある色落ちが生まれるのです。ヴィンテージに特有の立体的な色落ちは、この「中白」のおかげなのです。
一方、日本古来の藍染では、綿糸の一本一本の中心までしっかり藍を浸透させるべく、何度も染め直します。これにより全体的に均一に藍色が薄れていく、趣のある表情にはなりますが、デニムで求められるような明確なコントラストは生まれにくくなります。
ヴィンテージリーバイスが美しい色落ちを見せる理由は、適切な「中白」を持つ染色方法と、当時の生地の特性が組み合わさった結果と言えるでしょう。この染色技術は天然インディゴが使われなくなった後も受け継がれ、1970年代頃までのデニムは現代のものとは一線を画す美しい経年変化を見せるのです。
1978年以降、染色技術や生地の特性が変化したことで、色落ちのパターンも変わっていきました。それ以前のヴィンテージモデルの価値が高いのは、この「中白」による美しい色落ちが大きな理由の一つなのです。
まとめ:リーバイスの天然インディゴはいつまで使われていたのか振り返り
最後に記事のポイントをまとめます。
- リーバイスが天然インディゴを使用していたのは1920年初頭までで、それ以降は合成インディゴに切り替わった
- 501XXのような代表的なヴィンテージモデルも、1915年頃以降は合成インディゴで染められていた
- ヴィンテージの年代区分はXX(~1965年)、ビッグE(1966年~)、66前期(1969~1974年頃)、66後期(1974~1980年頃)に分けられる
- 「ピュアインディゴ」と「天然インディゴ」は別物で、前者は合成インディゴを指す
- 天然インディゴと合成インディゴは成分的には同じだが、前者は不純物を完全に取り除けないため色が薄くなる傾向がある
- 美しい色落ちの秘密は「中白」という染色特性にあり、表面だけを染めることでコントラストのある色落ちが生まれる
- 1978年頃を境に染色方法や生地が変わり、色落ちの特性も大きく変化した
- ヴィンテージとして真に価値があるのは1978年以前のモデルとされることが多い
- 503BSXXのような一部の復刻モデルでは天然インディゴが使用されたケースもある
- 天然インディゴで染めたデニムは色落ちしにくい特性があり、合成インディゴのものよりも高価になる傾向がある
- 66前期と66後期はバックポケット裏の縫製(シングルステッチvsチェーンステッチ)で見分けることができる
- トップボタン裏の刻印は年代判別の重要な手がかりとなる(1桁はヴィンテージ、2桁は80年代まで、3~4桁は80年代以降)
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- https://amvai.com/story/847
- https://jamtrading.jp/blogs/jam/1026500/
- http://girl.houyhnhnm.jp/fashion/the_vintage_denims.php
- http://eight-g.net/shopdetail/000000001908/
- https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q105604495
- https://channeltrutto.com/denim-9/
- https://www.pen-online.jp/article/009051.html
- https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1449136579
- https://rogers-kyoto.com/vintage_and_used/blog/post37065
- https://vintege-collection.hatenablog.com/entry/2022/01/17/205934
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。